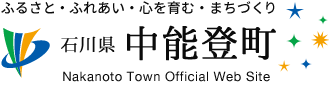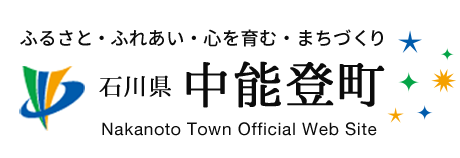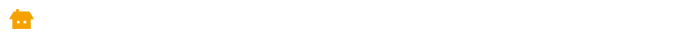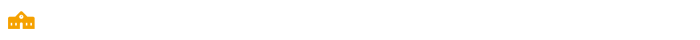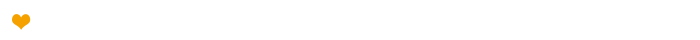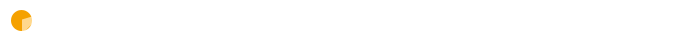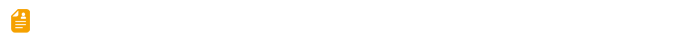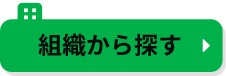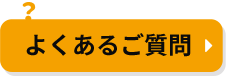被災住宅の応急修理制度について 【工事完了期限を再延長しました】
更新日:2024年02月22日
令和6年能登半島地震に伴う、災害救助法に基づく「被災住宅の応急制度」についてお知らせします。
実施期間
令和6年1月1日から令和6年12月31日まで
支援の内容
令和6年能登半島地震により被害を受けた住宅のうち、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」した世帯に対し、災害救助法に基づき被災した住宅の屋根、居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理する応急修理制度について、申込を受け付けています。
はじめに、ご自身で施工者を選定し、修理の箇所や内容を調整の上、市町に申し込んでください。選定された施工者に対し、町が修理を依頼します。
※既に修理に取り掛かっていても、本制度の対象となる住家については、施工者への支払いに至っていない場合、制度の対象にすることができます。
■ご注意 被災家屋などの解体・撤去【公費解体】制度との併用はできません■
住宅の応急修理制度は「引き続き、住家に住み続ける」ための制度のためです。
応急修理について(期限延長版) (PDFファイル: 412.0KB)
※損壊状況は、罹災証明にて確認します。
対象者
次のすべての要件を満たす方(世帯)が対象となります。
(1)当該災害により大規模半壊、中規模半壊、半壊及び準半壊等の住家被害を受けたこと。
災害により大規模半壊、中規模半壊又は半壊(半焼)若しくはこれに準ずる程度の住家被害を受け、そのままでは住むことができない状態にあること。
【「全壊」の場合でも修理により居住が可能となる場合は、対象となります。】
※納屋や車庫、空き家は対象となりません。
(2)応急修理を行なうことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。
※対象者(世帯)が、現に、避難所、車等で避難生活を送っており、応急修理を行うことで、被害を受けた住宅での生活が可能となることが見込まれる場合を対象とする。
応急修理の範囲
住宅の応急修理の対象範囲は、屋根や壁、床、ドア等の開口部の補修、上下水道等の配管など、居室、台所、トイレ等日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所となります。
基準額
1世帯あたり706,000円以内(準半壊は、343,000円以内)
※限度額を超える費用、対象外の工事部分の費用は自己負担となります。
手続きの流れ
申込みから修理完了までの流れ
- お申込みに必要な書類を全て揃えて町に提出します。
- 町から修理業者へ、手続きに必要な書類を郵送します。
- 工事完了後、必要な書類を提出してください。
応急修理制度の手続きの流れ (PDFファイル: 90.4KB)
申込み者からご提出いただく書類
申込み時
| 1 | 住宅の応急修理申込書 | 様式第1号(Wordファイル:39.6KB) | 様式第1号【記入例】(PDFファイル:178.8KB) |
| 2 | 罹災証明書※コピー可 | ー | ー |
| 3 | 施工前の被害状況が分かる写真 | ー | ー |
| 4 |
修理見積書 ※後日提出可だが、工事決定に必要 |
様式第3号(Excelファイル:27.5KB) | |
| 5 | 資力に関する届出書 | 様式第2号(Wordファイル:34.5KB) | 様式2 【記入例】(PDFファイル:124.3KB) |
| 6 | 住宅被害状況に関する申出書 | 被害状況申出書(Wordファイル:37.5KB) | 被害状況申出書【記入例】(PDFファイル:150KB) |
※修理業者向け説明会
修理業者からご提出いただく書類
工事の完了後
| 1 | 工事完了報告書 | 様式第7号(Wordファイル:30.5KB) | 様式第7号【記入例】(PDFファイル:111.3KB) |
| 2 | 修理前、修理中、修理後の写真台帳 | 参考様式1(Wordファイル:54.6KB) | ー |
| 3 | 修理見積書の写し ※変更の無い場合は不要 | ー | ー |
※修理業者向け説明会
工事完了報告期限
令和6年1月1日から12ヶ月以内(令和6年12月31日まで)
※状況に応じて延長の可能性があります。
その他の注意点
※掲載している情報は今後変更する場合もあります。
準半壊以上の被害を受けた住宅が対象です。制度の利用を検討されている方は、お手元の罹災証明書より被害の程度をご確認ください。
原則着工前に申請が必要ですが、早急に修理が必要な場合は、必ず施工前、施工中、施工後の写真を撮影してください。(写真がない場合、補助の対象とならない場合があります。)
応急修理は、町が業者に直接工事代金を支払う制度です(現物支給)。業者へ工事代金の支払いが完了してしまうと制度を利用することができませんので、ご注意ください。
借家等の所有者は、通常その所有者が修理を行うこととなっております。しかしながら、自らの資力をもって応急修理ができず、居住者の資力をもってしても修理ができない場合はご相談ください(所有者の所得、地震保険適用の有無、預貯金がない等、資力の確認について要件があります)。
便乗した悪質商法等にご注意ください!
- この記事に関するお問い合わせ先
-
土木建設課 町営住宅係
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎2階 住環境整備フロア)
電話:0767-72-3921 ファックス:0767-72-3929